七五三のお参りで欠かせないのが「初穂料」です。
しかし、のし袋や中袋の正しい書き方に悩む方は多いのではないでしょうか。
「金額はどう書けばいい?」「名前は子ども?親?」「中袋がない場合は?」──いざ準備を始めると、細かい疑問が次々と出てきます。
本記事では、七五三の初穂料を包む際の正しい中袋・外袋の書き方と渡し方のマナーをわかりやすく解説。
金額の書き方(大字)、子どもの名前の記入ルール、中袋がない場合の対応方法など、実際に役立つ具体例を交えて紹介します。
これを読めば、初めての七五三でも迷わず初穂料を準備でき、安心して神社に納められるはずです。
正しいマナーを身につけて、思い出に残る七五三を迎えましょう。
七五三の初穂料とは?基本の意味とマナー
七五三のお参りで欠かせないのが「初穂料」です。
そもそも初穂料とはどういう意味を持ち、どのような場面で使われるものなのでしょうか。
まずは基礎からしっかり整理していきましょう。
初穂料の由来と使われるシーン
「初穂料」とは、本来はその年に初めて収穫された稲や農作物を神様にお供えしたことに由来します。
お米や野菜を作っていない家庭では代わりにお金を納めるようになり、現在では神前に感謝の気持ちを表すための謝礼として定着しました。
七五三やお宮参り、安産祈願、交通安全祈願など、神社で祈祷を受けるときに納めるのが一般的です。
| 行事 | 初穂料を納める目的 |
|---|---|
| 七五三 | 子どもの成長を感謝し、健やかな未来を祈る |
| お宮参り | 誕生を祝い、無事の成長を祈る |
| 安産祈願 | 母子の健康と出産の安全を願う |
| 交通安全祈願 | 日常生活の安全を願う |
金額は神社ごとに決められている場合も多く、一般的には5,000円〜10,000円程度が相場とされています。
玉串料との違いを整理
「玉串料」という言葉を聞いたことがある方もいるかもしれません。
玉串とは榊(さかき)の枝に紙垂(しで)をつけたもので、神様にお供えするものです。
玉串を用意できない人のために、お金を納める形が「玉串料」になりました。
両者の違いを整理すると、初穂料は主に慶事(お祝い事)に使うのに対し、玉串料は弔事(お葬式など)にも使えるという特徴があります。
| 項目 | 初穂料 | 玉串料 |
|---|---|---|
| 使う場面 | 七五三・お宮参り・安産祈願など慶事 | 慶事・弔事どちらでも可 |
| 意味 | 初めての収穫物を神様に捧げる | 玉串の代わりにお金を捧げる |
| 注意点 | 弔事では使用不可 | 幅広い用途で使える |
七五三では必ず「初穂料」と記載するのが基本なので、混同しないように注意しましょう。
七五三の初穂料を包むのし袋の選び方
七五三で初穂料を納める際には、のし袋を正しく選ぶことが大切です。
どんな種類を選べばいいのか、購入場所や選び方のポイントを解説します。
水引の種類と意味(蝶結びと結び切りの違い)
のし袋を選ぶときにまず目に入るのが「水引」です。
七五三のようなお祝い事では紅白の蝶結びを選びます。
蝶結びは「何度でも結び直せる」ことから、子どもの成長や人生において繰り返し良いことが訪れるように、という願いが込められています。
一方、結婚式などで使われる結び切りはNGです。
「一度きりにする」という意味を持つため、七五三にはふさわしくありません。
| 水引の種類 | 意味 | 使用シーン |
|---|---|---|
| 紅白蝶結び | 繰り返し良いことがあるように | 七五三・出産祝い・入学祝いなど |
| 紅白結び切り | 一度きりで繰り返さない | 結婚式・快気祝い |
| 黒白結び切り | 二度と繰り返したくない | 葬儀・法要 |
七五三では必ず紅白の蝶結びを選びましょう。
購入場所と選び方のポイント
のし袋は、スーパーや文房具店、コンビニ、ホームセンターなどで手軽に購入できます。
近年では100円ショップにも種類豊富なのし袋が揃っているので、急ぎのときにも安心です。
選ぶ際のポイントは以下の通りです。
- 紅白の蝶結びであること
- 初穂料の金額に合ったサイズを選ぶこと
- シンプルなデザインのものが望ましいこと
特に金額が10,000円以上の場合は中袋付きのものを選びましょう。
中袋がないタイプは5,000円程度までが目安です。
神様に感謝を表すものなので、華美すぎる装飾の袋は避けるのが無難です。
七五三の初穂料の外袋の書き方
のし袋の外袋(表紙)は、最初に目に入る部分です。
神社の神職の方が確認する場所でもあるため、正しい書き方を心がけましょう。
表書きの正しい書き方(御初穂料/初穂料)
外袋の中央上部には、「御初穂料」または「初穂料」と縦書きで記入します。
筆ペンや毛筆を使い、濃く丁寧に書くのが基本です。
「御玉串料」や「御礼」と書く場合もありますが、七五三では「御初穂料」が最も一般的です。
| 表書きの文言 | 使用可否 | 注意点 |
|---|---|---|
| 御初穂料 | ◎ | 七五三やお宮参りで一般的 |
| 初穂料 | ◎ | よりシンプルに表現したい場合 |
| 御玉串料 | △ | 弔事にも使えるため避けるのが無難 |
| 御礼 | △ | 意味は通じるが正式度は低い |
書き間違えた場合は修正液を使わず、新しいのし袋を用意しましょう。
子どもの名前や連名の記載ルール
表書きの下、水引の中央下部には祈祷を受ける子どものフルネームを記入します。
大人ではなく、必ず子どもの名前で記載するのがマナーです。
読み間違いを防ぐため、ふりがなを添えるとより親切です。
兄弟姉妹で一緒に祈祷を受ける場合は連名で記載します。
このときのルールは以下の通りです。
- 年齢が上の子どもの名前を右側(上位)に書く
- 年齢が下の子どもを左側に並べる
たとえば「山田太郎」「山田花子」であれば、太郎を右、花子を左に配置します。
| 記載パターン | 例 |
|---|---|
| 単独 | 山田 太郎(やまだ たろう) |
| 兄妹 | 山田 太郎 山田 花子 |
| 姉妹 | 佐藤 美咲 佐藤 結衣 |
親の名前は書かないのが基本ルールなので注意してください。
七五三の初穂料の中袋の書き方【表面と裏面】
中袋は、お金を直接入れるための大切な部分です。
金額や住所を記載する場所なので、神社側が確認しやすいよう正しく書きましょう。
中袋の表面に書く金額(大字の例一覧)
中袋の表面中央には金額を縦書きで記入します。
正式には「大字(旧字体の漢数字)」を使うのが望ましいとされています。
| 数字 | 大字の書き方 |
|---|---|
| 1 | 壱 |
| 2 | 弐 |
| 3 | 参 |
| 5 | 伍 |
| 10,000 | 壱萬 |
たとえば5,000円なら「伍阡円」、10,000円なら「壱萬円」と書きます。
ただし、最近では「一万円」と通常の漢数字や「10,000円」とアラビア数字でも受け付けられる神社もあります。
不安な場合は、事前に参拝先の神社に確認すると安心です。
中袋の裏面に書く住所・氏名のルール
裏面左下には住所と氏名を記入します。
住所は郵便番号から書き始め、都道府県名から丁寧に縦書きします。
氏名はフルネームで記載し、こちらも祈祷を受ける子どもの名前を優先します。
| 記入項目 | 書き方の例 |
|---|---|
| 郵便番号 | 〒123-4567 |
| 住所 | 東京都新宿区〇〇1-2-3 |
| 氏名 | 山田 太郎 |
兄弟姉妹で祈祷を受ける場合は、連名で氏名を書きます。
住所が同じであれば1つだけ記載し、その下に兄弟姉妹の名前を並べればOKです。
書き忘れや空欄はマナー違反になるので注意してください。
中袋がない場合の初穂料の包み方
最近は中袋が付いていない簡易的なのし袋や、白封筒を使うケースも増えています。
その場合も書く内容や位置を正しく守ることが大切です。
白封筒を使う場合の正しい書き方
白封筒や中袋なしののし袋を使う場合は、外袋に直接必要事項を記入します。
- 表面上部に「初穂料」と縦書きで記入
- その下に祈祷を受ける子どものフルネームを記入
- 裏面左下に住所と金額を記入
このときも筆ペンや毛筆を使うのが基本です。
| 記入箇所 | 記入内容 |
|---|---|
| 表面上部 | 初穂料 |
| 表面下部 | 子どもの氏名(フルネーム) |
| 裏面左下 | 住所・金額 |
ボールペンは略式すぎるため避けましょう。
金額や住所の位置の注意点
金額は「伍阡円」「壱萬円」など大字で書くのが正式です。
ただし、白封筒の場合は「一万円」「10,000円」と記載しても受け付けてもらえることが多いです。
住所は縦書きで、都道府県名から省略せずに記載します。
裏面に金額と住所を必ず書くのを忘れないようにしましょう。
これは、受付で管理しやすくするための大切なマナーです。
七五三の初穂料のお金の包み方
のし袋や中袋に入れるお金の扱い方にもマナーがあります。
金額や書き方だけでなく、お札の種類や入れ方にも注意しましょう。
お札の種類と新札が望ましい理由
七五三の初穂料に包むお札は、できるだけ新札を準備するのが好ましいとされています。
新札は「清らかさ」や「誠意」を表し、神様への感謝を伝える気持ちを形にできます。
どうしても新札を用意できない場合は、折り目や汚れが少ないきれいなお札を選びましょう。
| お札の種類 | 対応 |
|---|---|
| 新札 | 最適。正式なマナーとして推奨 |
| 使用済みで綺麗なお札 | 可。ただし新札が望ましい |
| 破れや汚れのあるお札 | 不可 |
銀行で両替すれば、新札を準備しやすいので事前に確認すると安心です。
お札の向きと入れ方のマナー
お札を中袋に入れる際は、向きにも気を配りましょう。
基本のルールは、肖像画が中袋の表側に向くように入れることです。
つまり、中袋を開けたときに人物の顔が正面に出るようにします。
- 表:お札の表面(肖像画)が見えるようにする
- 向き:肖像画の上が袋の口側に来るようにする
この入れ方は「正しい向きで神様にお金を差し出す」という意味を持ちます。
お金を雑に入れるのは失礼なので、必ず揃えて入れましょう。
初穂料を渡すときのマナー
のし袋を正しく準備しても、渡し方に失礼があると台無しになってしまいます。
ここでは、初穂料を神社で渡す際のタイミングや所作のマナーを確認しておきましょう。
渡すタイミングとふくさの使い方
初穂料は祈祷の前後に受付で納めるのが一般的です。
神社によって流れが異なるため、受付で案内に従えば安心です。
のし袋は必ずふくさに包んで持参します。
| タイミング | 対応方法 |
|---|---|
| 祈祷前 | 受付で申し込み時に渡す |
| 祈祷後 | 御祈祷を終えてから渡す場合もあり |
渡すときは、ふくさからのし袋を出して両手で差し出します。
そのまま鞄から出して渡すのはマナー違反です。
誰が渡すべきか?両親と祖父母の考え方
初穂料は本来、子どもの両親が納めるものです。
ただし、近年では祖父母が準備するケースも増えています。
家庭ごとの考え方によって柔軟に対応して構いません。
- 両親が準備するのが基本
- 祖父母が負担してくれる場合も多い
- 一緒に参拝する場合は、どちらが出すか事前に相談しておく
どちらの場合でも、受付では祈祷を受ける子どもの名前で記載した袋を渡すのが正解です。
まとめ!七五三の初穂料の中袋の書き方を正しく守ろう
七五三で納める初穂料は、子どもの成長を願う大切なお供えです。
正しいのし袋や中袋の使い方を知ることで、神様への感謝の気持ちをより丁寧に伝えることができます。
| ポイント | 具体的な内容 |
|---|---|
| 外袋 | 表書きは「御初穂料」、水引の下に子どものフルネーム |
| 中袋 表 | 金額を大字(例:壱萬円、伍阡円)で記入 |
| 中袋 裏 | 住所と氏名を縦書きで丁寧に記入 |
| 中袋なし | 表に「初穂料」と子どもの名前、裏に金額と住所を記入 |
| お札 | 新札を用意し、肖像画を表にして中袋へ |
| 渡し方 | ふくさに包み、受付で両手で渡す |
最も大切なのは「丁寧な気持ち」を形にすることです。
書き方のルールを守ることで、安心して神社に初穂料を納められます。
正しいマナーを心がけて、思い出に残る素敵な七五三を迎えてください。
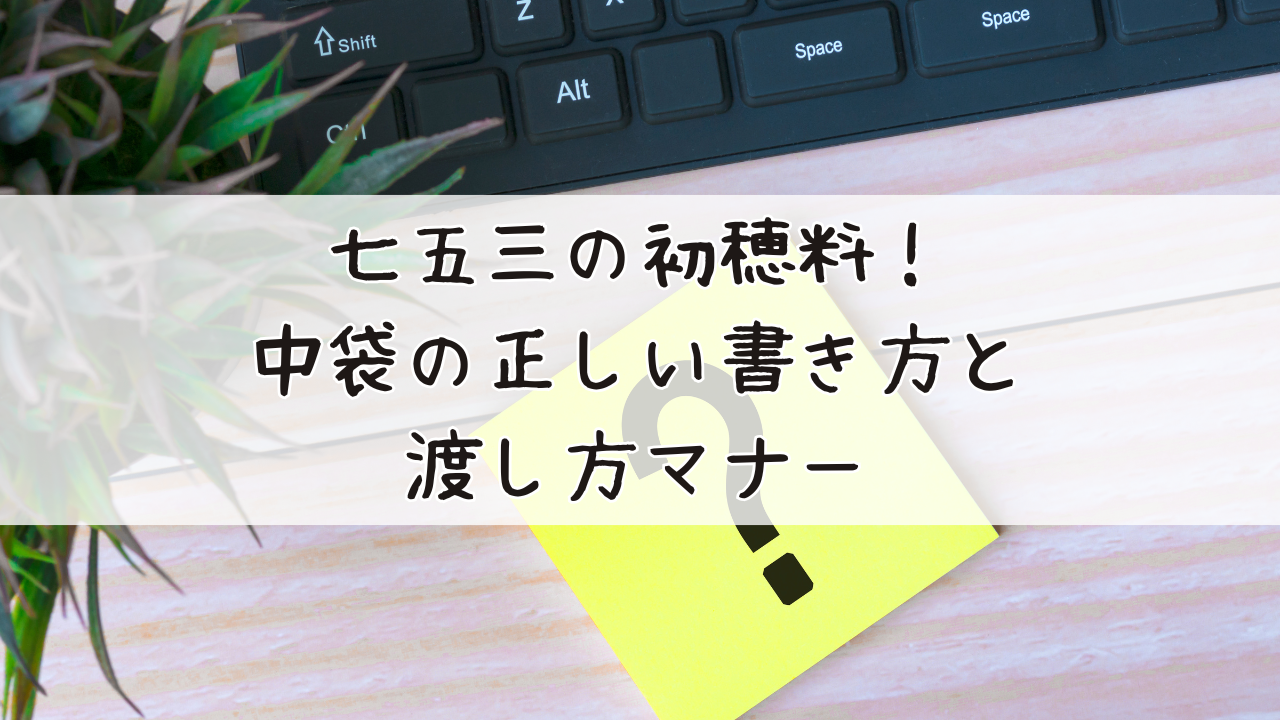


コメント